この記事では、ひろゆきさんの著書「このままだと、日本に未来はないよね。」を読んで感じた、僕が「日本教育について思うこと」について記述しています。
日本がオワコンとまで言われる原因について、「日本の義務教育におけるここが問題なんじゃないか」という視点での考察です。
あくまで、個人的な見解が中心です。
日本がオワコンだと思う理由
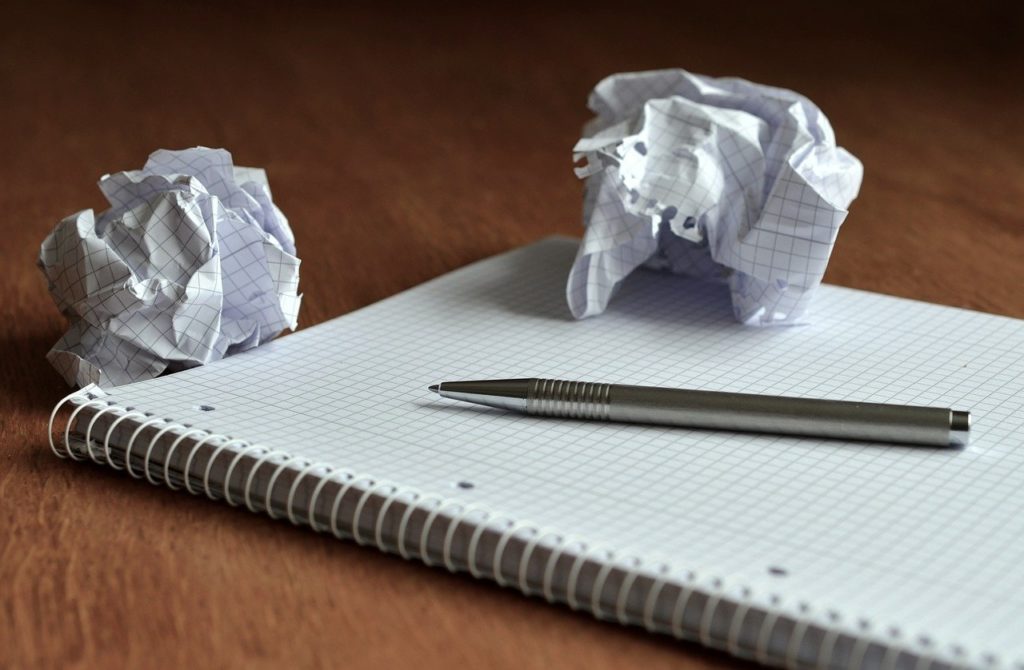
ひろゆきさんの著書「このままだと、日本に未来はないよね。」の中には「オワコン日本」なる言葉がたびたび登場します。
「日本がオワコン」な理由を、僕はこう思います。
日本教育が「ガラパゴス化」しているから
スマホ(スマートフォン)が普及し始めた頃を思い出してみてください。
スマホが普及するや否や、それまで聞き慣れない「ガラケー」という単語も浸透しましたよね。スマホに替えていないガラケーユーザーは、「え、まだガラケーなの」などと小馬鹿にされたりしたのではないでしょうか。
比較対象とされたそれまでの「ガラケー」ですが、語源はご存じの通り「ガラパゴス・ケータイ」です。
ガラパゴスとはWikipediaで以下のように記述されています。
ガラパゴス化(ガラパゴスか、Galapagosization)とは、日本のビジネス用語のひとつで、孤立した環境(日本市場)で製品やサービスの最適化が著しく進行すると、外部との互換性を失い孤立して取り残されるだけでなく、適応性(汎用性)と生存能力(低価格)の高い製品や技術が外部(外国)から導入されると、最終的に淘汰される危険に陥るという、進化論におけるガラパゴス諸島の生態系になぞらえた警句である。ガラパゴス現象(Galápagos Syndrome)ともいう。
Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%91%E3%82%B4%E3%82%B9%E5%8C%96)
僕は、このガラパゴス化(ガラパゴス現象)が携帯電話という分野のみならず、日本の教育にまで及んでいるのではないかと感じています。
「国際化」がうたわれ始めてからずいぶん長い期間が経過したように思いますが、果たして日本の教育はどれくらい変わったのでしょうか。
私には現在小学校1年生の息子がいますが、時間割表を見ても、私が小学校1年生の頃と比べて何が変わったのだろうと疑問を持ってしまうくらいに変化を感じることができません。
「こくご」、「さんすう」、「どうとく」、「たいいく」、「おんがく」、「ずこう」・・・
ね、至って普通でしょ。
それが、ちょうど、ひろゆきさんの著書「このままだと、日本に未来はないよね。」を読んだ頃のことです。息子の時間割を一緒にやっている時に、ふと「これがガラパゴスを引き起こしているのでは。」と思ったんです。
そう、ここ何十年も変わっていないと思われるあの教科です。
もう古い、「国語」という教科
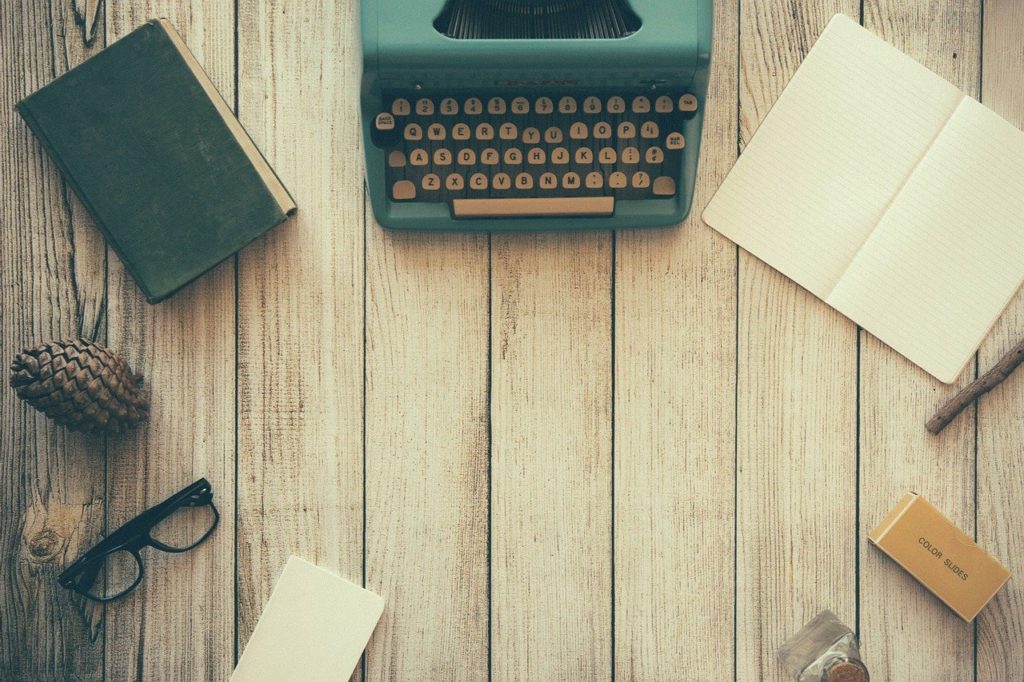
小学校や中学校の義務教育で必ず習う「こくご」や「国語」。
その歴史についてググってみたら、出てきました。これらの教科が設置されたのは、今から120年遡ること1900(明治33)年だそうです。
いやぁ、120年ですよ。
この間、多くの「日本人」が「国の言語」として「国語」の教科を勉強してきたんですね。愛国心の強い日本ですから、「国の言語」としたことにも何となくナットクです。
ただ、僕はこう考えます。
「Japanese(日本語)」を「国語=国の言語」として取り扱っているから、変化の激しい現代においては日本がますますガラパゴス化する。
時代はますますスピードを上げながら進んでいますよね。
海外で活躍する日本人が増えたように、日本を好み、日本に住み、日本で働く海外出身の方々がたくさんいます。まさに国際化が進んでいることを実感する日々です。
国際化が進む一方で、言語に関して見てみると、日本教育の「こくご」や「国語」は昔のままのような気がしてなりません。今や、日本人が言うところの「国語」は、海外の方々にとっては「日本語」や「ニホンゴ」であり、「Japanese」なのです。「国語」ではありません。
もう「国語」という教科は、考え方が古いのです。
「国語」という概念を捨てるべき
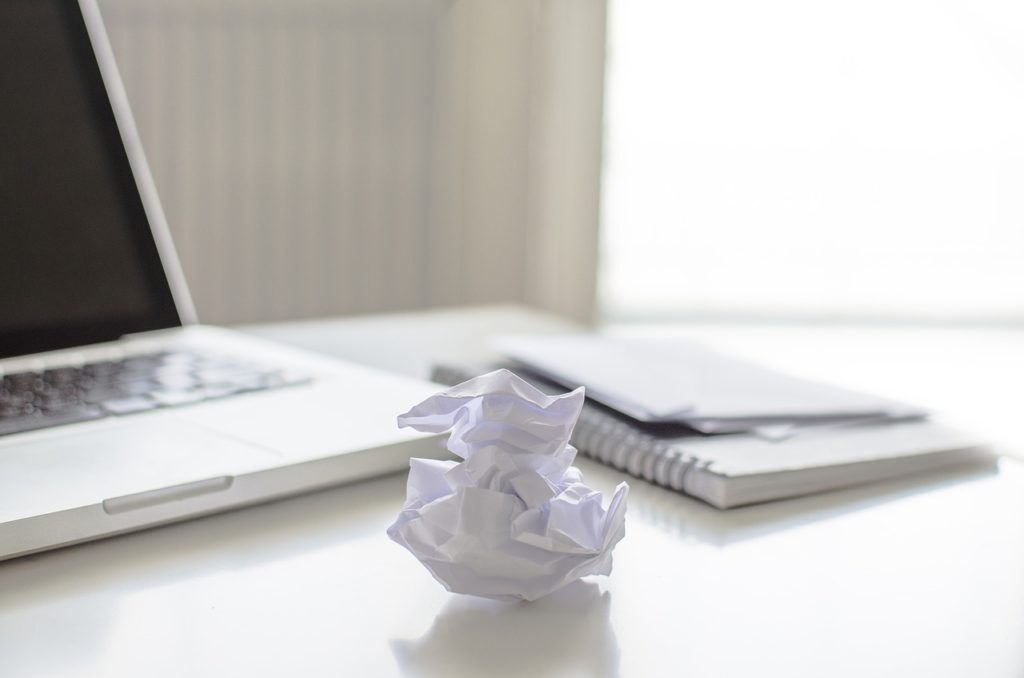
では、どうすればいいのか。
僕はこう思います。
- 「国語」という概念を捨てる
- 「日本語」(という教科)として見直すべき
ちょっとだけ、国語を客観的に見るために、英語をどう見ているのか考察してみます。
今の日本教育について我々は、どこか「英語」をオプション的に捉えていることはないでしょうか。
例えば、こんな感じ。
- 「小学校でも英語教育が始まった」という考え
- 「英語は試験のために勉強するもの」という考え
- 「英語は外国語(第2言語)」という考え
かく言う僕も正直に言って、まだまだそう捉えていることがあります。
ただこれまでは日本経済が強く、「先進国」として他国からも認めれてきたので、「日本人は日本語を話す」がある程度通用しました。無理に英語を話せなくてもよかったのです。
しかし、これだけ国際化が進んだ現代において、本当にそれは正しいでしょうか。
私は10年ほど前にインドに行った時に、「英語が通じないってなんて不便なんだろう」と思いました。自分が”そんなに流暢に英語を話せるわけではない”のにです。
インドも日本と同様、旧来からの言語を使うことがほとんどで、一部の方が英語を使っているイメージですが、それでも日本人以上に英語を使っているイメージが残っています。
幸い日本では識字率が高いですが、当時のインドの識字率は70%未満で、2020年現在でも75%ほどだどいいます。識字率が低いと、書いて伝えることも難しくなります。
こうした状況に置かれると、一切日本語は通用しません。結局、日本語、英語、ヒンディー語が分かる現地の通訳が同行していたことを思い出します。
海外において、我々日本人の「国語」は比較的容易に孤立してしまいます。
だから、これだけ国際化が進んだ現代において、「国語」という概念は無意味だと思うのです。
「英語」=「世界共通語」の概念を再認識するべき

一方で、英語は身に着ければ最強のアイテムです。
多くの国が「世界共通語」として、受け入れて使っています。
先にお話したインドのような状況下では、ほんの少しでもいいから英語が通じることを頼ります。中学校や高校で学んだほんのわずかな記憶に頼りながら、知っている単語を繋げて一生懸命に伝えようと必死になるのです。
同様のケースは日本国内でも珍しくなくなりましたね。
海外の方に外国語で話しかけられてオドオドした経験はありませんか。
こうした経験をすると、日本語しか話せない状況は辛いですよね。
やっぱり、英語を話せるようになりたいですよね。
これから日本が衰退することなく更なる発展を望むのならば、この考えが必要。
- 「英語」=「世界共通語」の概念を再認識するべき
- 「日本語」と「英語」という言語の2本立てを行うべき
英語が世界共通語と言われ始めてから、どれだけの年月が過ぎたでしょうか。
もはや、日本語を「国語」として扱っている場合ではありません。
日本が世界に埋もれて孤立しないためにも、英語をもっと取り入れていく根本的な改革が必要です。
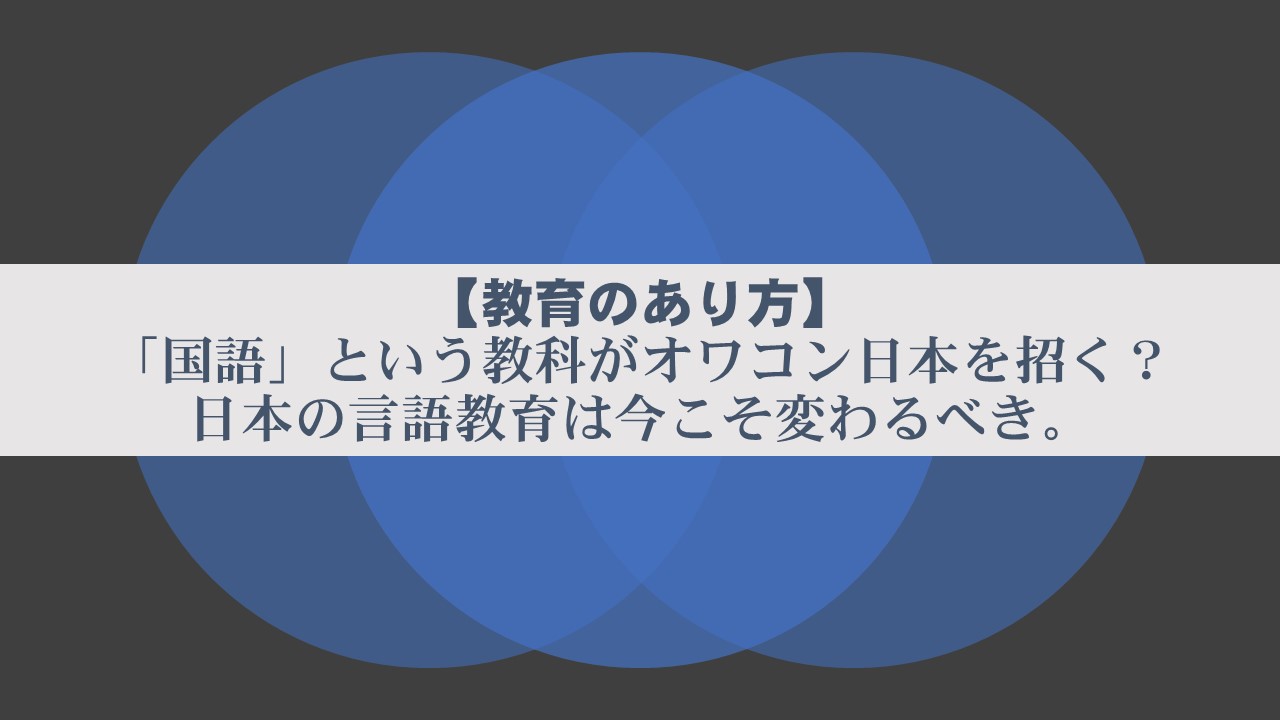
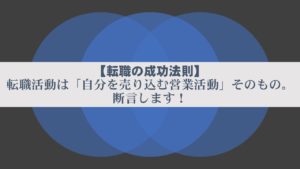

コメント